
熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)は、熊野信仰の中心地であり、全国に4700以上もある熊野神社の総本宮でもある格式の高い神社です。三本足が特徴の八咫烏(やたがらす)と縁深いことでも知られています。古来より人々の深い信仰が寄せられ、世界遺産に指定されたことで、その存在感をいっそう増しました。救いを求め蘇(よみがえ)りを願って熊野古道を歩み進んだ先にあるのが、熊野本宮大社です。
1. 世界遺産・熊野三山と熊野本宮大社

熊野本宮大社 は、熊野信仰の聖地と呼ばれています。熊野信仰とは、和歌山県南部から三重県南部の一帯・熊野と呼ばれる地域にある熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)をその象徴とします。長距離の移動そのものが困難だった太古から、憧れや救い、癒やしの対象とされてきました。
熊野三山の中でも、熊野本宮大社は、信仰の中心地です。熊野詣は、自然信仰に始まるとも、記紀の神話の頃からともいわれています。熊野詣は身分や性別を問わない懐の深さから、人々の信仰を集めてきました。日本で最も有名な神社のひとつに伊勢神宮がありますが、「伊勢に七度、熊野へ三度、どちらが欠けても片詣り」ともいわれます。
旧社地の大斎原(おおゆのはら)と熊野本宮大社を含む熊野三山、その参詣道の熊野古道は、「紀伊山地の霊場と参詣道」として、2004年7月7日に世界遺産に登録されました。今もなお、参詣客が途絶えることはありません。
基本情報
名称 熊野本宮大社
住所 和歌山県田辺市本宮町本宮
連絡先 0735-42-0009
URL http://www.hongutaisha.jp/
2. 日本全国にある熊野神社の総本宮・熊野本宮大社

2-1 御由緒・歴史
古くは記紀(古事記と日本書紀)に、天地開闢(てんちかいびゃく)の際、高天原に最初に登場した造化三神(ぞうかさんしん)の一柱、高御産巣日神(たかみむすひのかみ)が、神武東征にあたって八咫烏を使わし、初代天皇となる神武天皇を熊野国から大和国へと導いたと記述があります。
第十代崇神天皇のころ、旧社地の大斎原にある櫟(いちい)の大木に三体の月が降臨したといわれ、 中央が家都美御子大神(けつみみこのおおかみ)つまり素戔嗚尊(スサノオノミコト)が、月をともなって降臨したといわれています。両側の月は両所権現(熊野夫須美大神くくまのむすびのおおかみ〉と速玉之男大神〈はやたまのおのおおかみ〉)です。これが、大斎原に社殿が建てられた由来です。
奈良時代になると仏教を取り入れて神仏習合とし、熊野権現と称してご祭神に仏名を配するようになりました。平安時代には上皇、女院が熱心に熊野を訪れるようになり、その行列が熊野御幸と呼ばれるようになります。室町時代になるころには、武士や庶民の間にも熊野信仰が広まり、人々が競うように参詣したことから、「蟻の熊野詣」という社会現象を起こしたといわれています。
2-2 ご祭神

ご祭神は、熊野三山に共通の「熊野十二所権現」と呼ばれる十二柱の神々です。その中でも主祭神は、社殿を創るきっかけとなった家都美御子大神/素戔嗚尊。共に降臨した熊野夫須美大神と速玉之男大神に加えて、天照大神の四柱の神々を上四社でお祀りしています。そのほかの八柱は大斎原の石祠に祀られて います。
2-3 社殿

一の鳥居をくぐって参道を進み神門を抜けると、桧皮葺(ひわだぶき)で白木造りの社殿があります。明治22(1889)年に水害に見舞われながらも流出を免れた上四社は、2年後、現在地に遷座されました。 向かって左から「結宮(むすびのみや)」「証誠殿(しょうじょうでん)」「若宮(わかみや)」です。結宮には、熊野夫須美大神と速玉之男大神、証誠殿には家都美御子大神、若宮には天照大神が鎮座します。
2-4 宝物殿
宝物殿には、国や県の重要文化財に指定された熊野本宮大社の歴史の一部を感じさせる品々が展示されています。神事や儀式に使用されていた鏡や日本で2番目に古いとされる鉄湯釜、江戸時代に描かれたとされる旧社地の境内の絵図 など、室町時代と戦国時代の戦災や、明治時代の水害を免れた貴重な宝物です。
※2022年1月現在、休館中です。 →24年8月に再開されたようです。注釈不要ですかね?
2-5 八咫烏

三本足が特徴的な八咫烏は太陽の化身とされています。八咫は大きいという意味、三本足はそれぞれ「天・地・人」を表します。熊野本宮大社の主祭神・家都美御子大神のお使いです。日本サッカー協会のマークに採用されています。神武天皇を熊野国から大和国へと導いたことにちなんで、勝利やボールをゴールへと導くという願いが込められているのでしょう。境内に八咫烏ポストが設置されており、授与所にて授与している「八咫烏ポスト絵馬」をハガキとして郵送できます。
2-6 授与品・御朱印
お札や八咫烏のお守り、御朱印などを受けることが可能です 。神社は年中無休。
2-7 お祭り

毎年4月13~15日にかけて開催される例大祭・本宮祭 がもっとも賑わいます。15日には、神々が旧社地に還られる、渡御祭 が行われ、大斎原に向かう大行列が、かつての熊野御幸を彷彿とさせます。大斎原でとり行われる、舞や神事なども見どころです。
11月下旬には、八咫の火祭りがこだま祭りと同日開催されます(※1) 。八咫烏の導きの逸話から、人々を幸福に導くことを願うものです。神事の後、炎の神輿とともにつぼ装束 に身を包んだ女性や山伏などが連なる時代行列には一見の価値があります。地元有志の和太鼓や花火がお祭りをいっそう賑やかにします。
※1 令和2年より感染症蔓延防止のため斎行を中止しています。 →2023年から再開されています。注釈はトルでよいと思います。
2-8 熊野本宮大社の周辺施設

熊野本宮大社の周辺には、見ておきたい史跡や博物館があります。旧社地の大斎原にあるのは、高さ34m、幅約42mという日本最大 の鳥居です。近隣には、世界遺産熊野本宮館や和歌山県世界遺産センターもありますので、時間のある方やもっと詳しく知りたい方は訪ねてみましょう。
3. 古の人々の歩みを辿る熊野古道

熊本宮大社の別の楽しみ方に、熊野古道から歩いていく方法があります。古の人々がどのようなルートで熊野を目指したのか、体感してみるのもよいでしょう。熊野古道には、6つのルート がありますが、その中でもっとも人気のあるのが中辺路 (なかへち)です。
紀伊田辺駅から熊野本宮大社までの長く険しい山道ですが、熊野信仰がもっとも盛んになった平安時代には、皇族が100回以上も参詣したという熊野御幸から御幸道とも呼ばれるようになりました。
伊勢路には、熊野本宮大社の主祭神・家都美御子大神/素戔嗚尊の母である伊弉冉尊(いざなみのみこと)が葬られたとされる花の窟(はなのいわや) があります。高さ約45mという切り立った崖のような巨岩がご神体。こちらも世界遺産です。
4. 旅人の疲れを癒やす熊野本宮温泉郷

疲れた体を癒やしてくれるのが、熊野本宮温泉郷。湯の峰温泉と川湯温泉、渡瀬温泉という三つの温泉からなっています。
湯の峰温泉は、開湯1800年という歴史を誇ります。古来、熊野を目指す人々は、参詣の前に旅の疲れを癒やし、湯垢離(ゆごり)で禊をして備えました。天然の岩風呂「つぼ湯」は、熊野詣の参詣道の一部として世界遺産に登録されています。お湯の色が7色に変化する変わることから、七色の湯とも呼ばれます。
川原を掘ればたちまち温泉が湧き出る川湯温泉は、70℃を超える源泉に大塔川の水が混ざり適温になる仙人風呂が有名です。川の水をせき止めた浴槽のため、天候などの条件により、入浴できないこともあります。期間は12月から2月末日まで。
わたらせ温泉では、露天風呂を堪能できます。温泉センターもあり、キャンプやBBQも楽しめますよ。
5. 熊野三山を巡るならツアーへの参加がおすすめ
熊野本宮大社は熊野三山だけでなく熊野信仰の中心地でもあります。その歴史は古く、神話の時代から奈良時代、平安時代に幾代もの皇族が熱心に詣でた時代から現代まで、連綿と続いています。杉木立に包まれた霊場と呼ばれる信仰の地、人々の思いが集まる場所へと赴き、2000年を超える時の流れを感じてみてはいかがでしょうか。個人での三社巡りはなかなか大変なので、ツアーで巡るのがおすすめです。
![]()
とりっぷナビ編集部
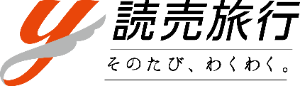







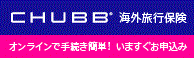

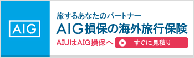
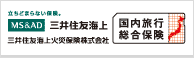




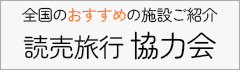



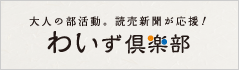

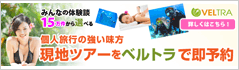
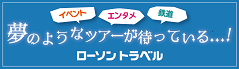

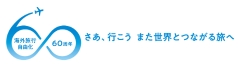




観光情報や旬のイベント、グルメなど旅にまつわる情報を発信しています!